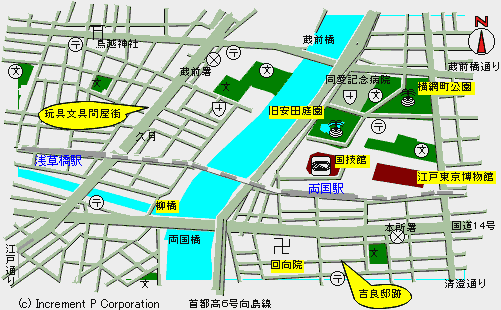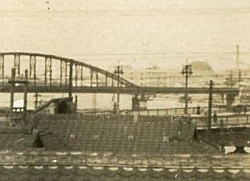
 両国公会堂近影
両国公会堂近影 こだま通信9号番外編
3月10日の大空襲の話はすでに9号の中で触れてきました。すこし詳しく説明しますと、1945年3月9日から10日に日付が変わった直後にB-29爆撃機325機(うち爆弾投下機279機)が東京上空に侵入、午前0時7分に深川地区へ初弾が投下され、その後、城東地区にも爆撃が開始されました。0時20分には浅草地区でも爆撃が開始されています。この大空襲の中では大勢のひとびとが亡くなっているのですが、この時の被災者で身元不明の方が東京都の震災記念堂に祀られています。
私の父方の叔父も戦火にまきこまれながらも奇跡的に助かったという話を聞いております。 私が聞いた話は、この叔父は大勢の方が亡くなった場所(本所公会堂近くの公園地下室)にいったんは避難したのですが、風向きが変わったのを察知して方向を変えてその場所を離れたために命拾いをした、というものです。この叔父は「京金」という屋号で蕎麦屋を営んでおり、戦後も森下でその商売を続け、最終的にはその子供がJR錦糸町駅の駅ビルの中でも同名のそばやを出店しています。その子供たちというのは父のいとこに当たるわけですが、「ひろさん」という名前です。この人に関する記憶は江東区の森下に引越しをした当時のもので、でっぷりと腹が突き出した人という印象が残っています。私と母はこの蕎麦屋にちょくちょく行ったらしく、今でもお店の雰囲気を話せます。私たち兄弟は体型が似ていて、弟を見ているとこの父のいとこ「ひろさん」を思い出します。
不思議な話は世の中にいっぱいありますが、私もこの父方の叔父の話に関連して不思議な体験をしました。それは数年前に還暦を記念してドームホテルに泊まりがてら江戸東京博物館に行ったときの話しです。館内の体験コーナーで「肥え桶」をかつぐところがあるのですが、その肥え桶をかついでベンチに座った時の話です。となりに座っていた老婦人がわたしに話しかけてきたのです。そもそもこの肥え桶は戦後の食糧難を乗り越えるために、庶民が庭に畑を作ったときに必要なものなのですが、その老婦人はそのころの思い出話をしはじめました。 その中で、その方のご主人のお父さんの話をしてくれました。その話をかいつまんで言いますと、その内容は「京金」の話とそっくりなのです。 その老婦人はご主人と一緒に横浜に住んでおり、その子供たちが現在のおそばやさんを受け継いでいるとのことでした。つまり子供さんというのは私と同年輩になるわけです。
私はあまりの類似性にお名前を聞くのもためらってしまいました。私の子供のころ、「京金」の帳場(レジ)に座っていたのは「ひろさん」の母上であり、「ひろさん」は板場(厨房)でそばを打っていたのでしょう。その「ひろさん」は余生を横浜で送っているというわけです。 私の父が商売に失敗し、森下の家から向島に引越すはめになった理由のひとつとして、この家の土地が「ひろさん」からの借地だったためと聞いています。 「ひろさん」からの借金の担保として家を抵当に入れたため、借金を返せないために手放したものでしょう。 お金の貸し借りの話ですから、やむを得ない話ではあるのですが、当時の子供の頭ではそれは理解できるものではなく、なんと世の中は理不尽なものだと子供心にも思ったものです。そのしこりが老婦人へお名前を確認することをためらったのだと思います。
この話を家内に話したのですが、一蹴されてしまいました。幽霊じゃあるまいしそんな出来すぎた話があるわけが無いというのです。 しかしこの話を思い出すたびに背筋がぞっとするのです。
1935年ごろの本所公会堂(現・両国公会堂)
手前の屋根は密集した民家。
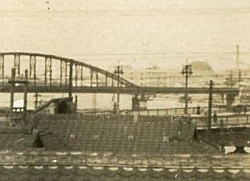
 両国公会堂近影
両国公会堂近影
1933年(昭和8年)頃の震災記念堂 右下が復興記念館、
右上に本所公会堂(両国公会堂)や旧安田庭園が見える
[一九三三
大東京寫眞案内(博文館)]